海外に憧れることは“逃避”なのか? ―ファンタジーに憧れる人々との比較から考える
SNSでよく目にする「海外移住したい」「フランスでカフェを経営したい」「イタリアの海沿いで暮らしたい」――こうした発言を目にするたびに、ある種の違和感を抱く人は少なくありません。なぜ、わざわざ海外を「理想郷」のように語るのか。そこに現実への不満や、日常に対する不適応が見え隠れするとき、つい「それって本当に幸せなの?」と問いたくなることもあるでしょう。
一方で、ファンタジー世界に憧れる男性や女性もまた、現実からの“逃避”として非日常の世界に夢を抱いています。しかし、両者には微妙な違いがあります。本稿では、海外志向の女性とファンタジー世界を愛する人々を比較しながら、その心理の構造と可能性について考察していきます。
なぜ海外に惹かれるのか?
海外への憧れの根底にあるのは、「今の自分の環境に満足できない」という感情です。特に日本社会では、女性がキャリアと家庭の両立を求められ、時に「普通であること」に対する重圧が強くのしかかります。
「もっと自由に暮らしたい」「縛られたくない」「個性を認められたい」――そういった欲求が、「海外」というフィルターを通して、美化された理想郷として認識されるのです。そこには、SNSで見かけるヨーロッパのカフェや美しい街並み、自由を謳歌するような生活写真の影響もあるでしょう。
けれども、こうしたイメージは現地の“日常”ではなく、あくまで観光者目線、もしくは編集された非日常の断片にすぎません。実際に移住した人の多くが「理想と現実のギャップ」に悩むことは、様々な体験談からも明らかです。
ファンタジー世界に惹かれる人々との違い
興味深いのは、ファンタジー世界に憧れる人々は、それを「現実にする」つもりは最初からないという点です。
例えば、剣と魔法の世界に心を躍らせるオタク男性、あるいは王子様との恋に胸をときめかせる女性。彼らは「現実とは違う世界がある」ということを知っており、それを夢見ることでストレスを発散し、むしろ現実生活に折り合いをつけて生きています。
ファンタジーは、自己完結型の想像世界です。そこに浸っている間は現実の不満を忘れられますが、終わった後には日常に戻る準備ができている。一方、「海外=救い」と捉える人々は、夢と現実の境界が曖昧になっており、「現実逃避」のまま行動に移してしまう危険性があります。
共通する「ドーパミン依存」という問題
海外にしろファンタジーにしろ、根底には「非日常を求めるドーパミン志向」があります。新しい景色、新しい文化、新しい自分になれる予感――これらは一時的な快楽を与えてくれます。
しかし、ドーパミンは報酬系ホルモンであり、「手に入れた瞬間に消える」性質を持っています。海外に移住しても、ファンタジーの続きを読んでも、次の刺激を求め続ける限り、心は満たされません。
本当に満たされた人間は、目の前の現実を愛せるようになります。日本の四季を楽しむ。近所のパン屋に幸せを感じる。仕事に誇りを持つ。そういった「日常に幸せを見出す感覚」は、ドーパミンではなく、セロトニンやオキシトシンといった“穏やかな幸福”に根ざしています。
結局、海外に行くこと自体は悪いのか?
ここまで読むと、「海外に行く人を全否定するのか?」と思われるかもしれません。しかし、そうではありません。自分の意志で言語を学び、文化を知り、覚悟を持って新天地に挑む人々はむしろ尊敬に値します。
問題は、「今の自分の不満から逃れるために」「外の世界ならすべてうまくいくはず」という“空想の延長”として海外を選ぶ場合です。ファンタジーの住人がその世界に永住しようとは思わないように、海外を「理想郷」にしてしまうと、現実とのギャップに押しつぶされてしまうのです。
結論:憧れを夢で終わらせるか、現実に変えるか
憧れること自体は、人間らしく健全なことです。ただし、それが「現実の否定」になってしまったとき、人生は不安定になります。
ファンタジーに逃げる人は、ある意味で賢く、自己完結しています。海外に逃げようとする人は、現実からの“物理的脱出”に希望を託すため、リスクも高い。その差を理解したうえで、夢を追うか、現実と向き合うかの選択をすることが大切です。
「今ここ」にある幸福を感じられる力。それがあれば、海外に行かなくても、剣と魔法の世界に行かなくても、人はちゃんと幸せになれるのかもしれません。



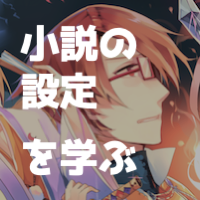








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません