美味しい洋菓子について紹介!物語を彩る小物
甘い生クリームたっぷりのケーキに、甘い缶コーヒーやジュース。
あなたはお好きでしょうか?
どんなにお腹がいっぱいでも、つい食べたくなる甘いものですが、食べすぎると様々なデメリットも発生します。例えば活性酸素が増加して老化を促進するとも言いますし、イライラしやすくなったり、果には糖尿病にもなります。(平安時代、フルーツや白米、甘い日本酒を好きなだけ食した藤原道長は、日本最古の糖尿病患者と言われています)
けれど目の前にホイップクリームたっぷりのマリトッツォが置かれていたら、そういったデメリットは置いておいて手を付けてしまいます。
さて、現実世界ではこのように自粛しようとすることもある(そして概ね失敗する)糖分ですが、物語の中では無限に食べることができます。ただただ甘いものを食べるだけの飯テロ小説があってもいいんじゃないでしょうか。
恋愛小説を書く上でもデートのシーンで甘いものは必ず登場するでしょう。甘いものが好きという共通点から物語が始まることだってあります。本エントリーでは、そんな甘い物語のための洋菓子の知識を紹介します。
- 1. 洋菓子とは?
- 2. 洋菓子と和菓子との違いは?
- 3. 洋菓子の分類
- 3.1. ・スポンジケーキ類(ショートケーキ、ロールケーキ、トルテ、デコレーションケーキ)
- 3.2. ・バターケーキ類(パウンドケーキ、フルーツケーキ、バターケーキ、チーズケーキ、バームクーヘン)
- 3.3. ・シュー菓子類(シュークリーム、エクレア、サントノーレ)
- 3.4. ・発酵菓子類(サバラン、ババ、デニッシュペーストリー)
- 3.5. ・フィユタージュ類(タルト、ミルフィーユ、フラン、フルーツパイ)
- 3.6. ・ワッフル類
- 3.7. ・シュトルーゼ類(パンケーキ、クレープ、プディング、ババロア、ゼリー、ムース、パルフェグラッセ)
- 3.8. ・砂糖漬類(オレンジピール、レモンピール)
- 3.9. ・キャンデー類(ドロップ、キャラメル、ボンボン、ゼリービーンズ)
- 3.10. ・チョコレート類(ソリッドチョコ、カバーリングチョコ)
- 3.11. ・チューインガム類(味ガム、風船ガム、キャンデーガム)
- 3.12. ・ビスケット類(クッキー、ビスケット、クラッカー、ブレッツエル、ウエハース、乾パン)
- 3.13. ・ドーナツ類(ドーナツ)
- 3.14. ・スナック類(ポテト系、コーン系、小麦粉系)
- 4. まとめ
洋菓子とは?
洋菓子とは、西洋に起源をもつお菓子の総称です。対になる言葉は、日本の伝統的なお菓子である和菓子です。洋菓子の原材料は、卵やバター、牛乳といった動物性の材料が多く使われます。
歴史的には、古代エジプトで紀元前10世紀頃にパン生地にレーズンや蜂蜜をトッピングした菓子パンのようなものが出現しました。紀元前1世紀頃の古代ローマには菓子職人がおり、プリンの原型であるトリヨンという菓子や、クッキーのようなもの、菓子パンや砂糖菓子も作られていたようです。
日本に洋菓子が入ってきたのは室町時代1543年、ポルトガル人からでした。「クッキー」「カステラ」「金平糖」が持ち込まれました。当時の日本では砂糖が貴重品で、庶民は甘い洋菓子に心を奪われたようです。
明治時代に入ると日本でも砂糖が大量生産され、庶民も砂糖を得ることができるようになりました。明治から現代にかけて、砂糖は身近になり、今では砂糖たっぷりの生クリームをつかったスイーツが食べられるようになりました。
洋菓子と和菓子との違いは?
洋菓子と和菓子との違いは材料にあります。
和菓子の原材料は、米や麦、豆類といった植物性の材料が主流で、動物性の材料を使う洋菓子と違いがあります。
洋菓子の素材は主に
・卵
・バター
・牛乳
・小麦粉
・チーズ
・砂糖
からできており、一番の特徴は水を使わないことです。
(卵のように熱を与えると凝固する素材を使うので、水を使わない)
そのため、和菓子よりも甘く仕上げることができます。
現代は大事な場面で和菓子よりも洋菓子のほうが使われます(友人へのプレゼント、お中元、お歳暮、結婚前の両親への手土産など)。
糖分は甘い麻薬とも言われるほど、脳に快楽を与えます。まさに現代の誰もが好きになってしまう「魔法のアイテム」なのですね。
洋菓子の分類
現代において洋菓子は、お菓子の水分含量を基準にして生菓子と半生菓子と干菓子に分類されます。
一般には水分を30%以上含むものは生菓子、水分が10~30%のものは半生菓子、水分が10%以下のものが干菓子とされます。それぞれの代表的なお菓子を下記にまとめます。
| 分類 | 例 |
| 生菓子 | ・スポンジケーキ類(ショートケーキ、ロールケーキ、トルテ、デコレーションケーキ) ・バターケーキ類(パウンドケーキ、フルーツケーキ、バターケーキ、チーズケーキ、バームクーヘン) ・シュー菓子類(シュークリーム、エクレア、サントノーレ) ・発酵菓子類(サバラン、ババ、デニッシュペーストリー) ・フィユタージュ類(タルト、ミルフィーユ、フラン、フルーツパイ) ・ワッフル類 ・シュトルーゼ類(パンケーキ、クレープ、プディング、ババロア、ゼリー、ムース、パルフェグラッセ) |
| 半生菓子 | ・スポンジケーキ類 ・バターケーキ類 ・発酵菓子類 ・砂糖漬類(オレンジピール) |
| 干菓子 | ・キャンデー類(ドロップ、キャラメル、ボンボン、ゼリービーンズ) ・チョコレート類(ソリッドチョコ、カバーリングチョコ) ・チューインガム類(味ガム、風船ガム、キャンデーガム) ・ビスケット類(ビスケット、クラッカー、ブレッツエル、ウエハース、乾パン) ・ドーナツ類(ドーナツ) ・スナック類(ポテト系、コーン系、小麦粉系) |
・スポンジケーキ類(ショートケーキ、ロールケーキ、トルテ、デコレーションケーキ)
小麦粉・鶏卵・砂糖を主な原料としてスポンジ状に焼いたお菓子。生クリームを塗ることで真っ白なショートケーキやデコレーションケーキになる。
キメ細やかで丈夫なスポンジ生地を作るコツは、材料を混ぜるときに大きな泡を作らないこと。ゆっくりとかき混ぜることで大きな泡ができるのを防ぐことができる。
・バターケーキ類(パウンドケーキ、フルーツケーキ、バターケーキ、チーズケーキ、バームクーヘン)
バターを多めに配合し、小麦粉・卵・ベーキングパウダー等と混ぜ合わせた生地を焼いて作るケーキ。きめが細かくずっしりと密度が高く、水分が少ない。
※チーズケーキはバターを入れずに生クリームで作られる場合があるが、生クリームはバターよりも水分量が多いため柔らかく仕上がる。バターでつくるメリットは硬い食感が得られること。
・シュー菓子類(シュークリーム、エクレア、サントノーレ)
バター・薄力粉・卵を材料を混ぜ合わせて煮上げた後に加熱して膨らませたシュー生地に、カスタードクリームなどを包んだお菓子です。家庭でつくる難易度は高めで、生地が膨らまないこともしばしば。ポイントは焼き上がるまで温度を下げないことです(オーブンの中を途中でのぞいたりすると失敗しがち)
・発酵菓子類(サバラン、ババ、デニッシュペーストリー)
「酵母」が存在する生地をゆっくり時間をかけて発酵させ焼き上げるケーキやクッキー、甘いパンです。
・フィユタージュ類(タルト、ミルフィーユ、フラン、フルーツパイ)
パイ生地をつかったお菓子です。パイ生地は 小麦粉、水、塩で小麦粉の生地を作りバターを包んで折り込んでいきます。薄力粉と強力粉を半々で使うとサクサクした感じを出すことができます。
・ワッフル類
焼き菓子です。小麦粉、卵、バター、牛乳、砂糖、イーストなどを混ぜて醗酵させて作った生地を、格子模様のある2枚の鉄板に挟んで焼き上げます。冷えると固くなってしまうので、それが嫌なら作りたてを冷凍し、食べる前にレンジでチンがおすすめです。
・シュトルーゼ類(パンケーキ、クレープ、プディング、ババロア、ゼリー、ムース、パルフェグラッセ)
詰め物のまわりに生地を幾層にも巻く甘い菓子です。例えばクレープは薄力粉、砂糖、牛乳、卵を200度の鉄板で焼いて巻いていきます。中に詰める食材次第で味は無限大です。
・砂糖漬類(オレンジピール、レモンピール)
給水作用のある砂糖で、対象の食材を包むことで、食材の雑菌や組織内の水分を糖分と交換して保存できるようにしたお菓子。最終的には40%〜50%は糖分になる。砂糖漬けの作業過程で食材を砕きゼリー状にするとジャムになる。
・キャンデー類(ドロップ、キャラメル、ボンボン、ゼリービーンズ)
砂糖を主材料とする洋風のあめ菓子。型にはめて作ることで、自由に形を変えることができます。
・チョコレート類(ソリッドチョコ、カバーリングチョコ)
カカオマス(カカオの種子を発酵・焙煎したもの)に砂糖、ココアバター、粉乳などを混ぜて練り固めたお菓子です。カカオ分40%〜60%を「スイートチョコレート」、カカオ分60%以上を「ビターチョコレート」もしくは「ダークチョコレート」と呼びます。カカオマスから油分だけを絞り出した透明な「カカオバター」に色を付けることでホワイトチョコレートや抹茶チョコレートをつくることができます。
・チューインガム類(味ガム、風船ガム、キャンデーガム)
ガムベースに味や香りをつけたお菓子です。ガムベースは、かつてチクルという天然樹脂から作られていましたが、現在はエステルガムのほか酢酸ビニル樹脂やポリイソブチルを含む合成樹脂も使われているようです。現代のガムはほとんどプラスチックの仲間です。環境に悪いのではということで天然素材をつかったガムが脚光をあびてきています。
・ビスケット類(クッキー、ビスケット、クラッカー、ブレッツエル、ウエハース、乾パン)
小麦粉に牛乳、ショートニング、バター、砂糖などを混ぜて、サクサクした食感に焼いたお菓子です。サクサクのクッキーをつくるコツは、水分と小麦粉が混ざった状態のクッキー生地を混ぜすぎないことです。ボウルに材料をいれたら、混ぜるときはボウルの中心で数字の1を書くようにするとよいそうです。
・ドーナツ類(ドーナツ)
小麦粉が主成分の生地に水・砂糖・バター・卵などを加えて、油脂で揚げたお菓子です。揚げる際に熱の通りを良くするために円形の生地の真ん中を丸く抜いて輪(トーラス)にしたリングドーナツ、棒状に伸ばした生地をねじったツイストドーナツ、穴を開けない球形あるいは扁平球形のものや棒状のものなどがあります。
・スナック類(ポテト系、コーン系、小麦粉系)
じゃがいもや穀類などを主原料とした、水分の少ないさくっとした食感の揚げ菓子です。他の洋菓子と違い、塩味が強いのが特徴です。塩もまた砂糖と同じように食べ始めたら止まらない魔法の食材ですね。ポテトチップスはお菓子の王です。
まとめ
本エントリーでは洋菓子について紹介しました。洋菓子にはたくさんの種類があることもわかりましたね。みなさんはどの洋菓子が好きでしょうか。
ぜひあなたの作品で洋菓子をつかった甘い物語を書いてみてください。もしできたらコメント欄でも教えて下さいね。


















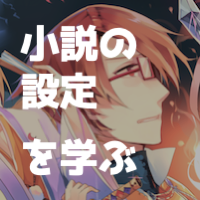







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません