「生殺与奪の権を他人に握らせるな!!」に学ぶ、台詞づくりのポイント
鬼滅の刃のアニメをAmazonプライムでようやく全て視聴しました。
(至れり尽くせりのAmazonプライム会員に登録しよう(解除も簡単))
ufotableさんの表現力、描写力に魅了され、夢中になって最後まで見ました。炭治郎の前向きな狂いっぷりも、私の好みです。
さて、この鬼滅の刃ですが、電子版を含むコミックスのシリーズ累計発行部数が、1億部を突破することが2020年9月24日に明らかになったとのこと。
テレビアニメが開始される前は累計350万部だったということで、凄まじい躍進ですね。
「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載された吾峠呼世晴(ごとうげ・こよはる)さんのマンガ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」の電子版を含むコミックスのシリーズ累計発行部数が、1億部を突破することが9月24日、明らかになった。10月2日発売の最新22巻で1億部を突破する。
<鬼滅の刃>コミックス累計1億部突破 「こち亀」「ドラゴンボール」「ONE PIECE」に続く快挙 最新22巻は初版370万部
(中略)
テレビアニメ開始時の2019年4月のシリーズ累計発行部数は約350万部で、約1年半で約29倍と破竹の勢いで部数を伸ばしている。2019年10月4日に第17巻が発売された際の累計発行部数は1200万部以上、同年12月4日の第18巻の発売時は2500万部以上、今年2月4日の第19巻の発売時は4000万部以上、5月13日の第20巻の発売時は6000万部以上を記録。7月3日に発売された第21巻で8000万部を突破した。
あとからならば何とでもいえるのですが、私たちのような創作者であれば、鬼滅の刃 第1話の時点で、この結果(1億部突破までは予想できないにしろ、各巻100万部突破くらいまでは)が予想できたのではないでしょうか。
理由は圧倒的な台詞の力です。
生殺与奪の権を他人に握らせるな!! の威力
連載でも第1話で登場した冨岡義勇の「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」から続くこの台詞。私なんかはこの台詞を読んだだけで、カナヅチに頭をぶっ叩かれたような衝撃を受けました。
「生殺与奪って、言葉としては知っているけど話したことがない……。権利じゃなくて権とした発想がすごすぎる……。他人に人生をコントロールさせるなというのは、ビジネス本なんかでも書かれていることでもあり、私自身も病気をしてたどり着いた人生の真理だ……。それがたった一言の台詞に凝縮されている……なんだこの才能は!」
第一印象は以上のような感じ。
「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」のあとに畳み掛けるようにして放った台詞や、冨岡義勇の独白も凄いですし、冨岡義勇が実は寡黙なキャラクターだったということもこれらの台詞に重みを与えています。
一連の台詞の内容と、それを冨岡義勇に言わせたこと。これらの設計に、吾峠呼世晴先生の凄まじい才能を見せつけられ、圧倒的な力量差を感じて放心状態になりました。
しかしそのきっかけは、「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」という一言目でした。この台詞がなければ、その後の長い台詞は説教臭さを感じたかもしれません。一言目が圧倒的に強いのです……台詞の力がありすぎます。売れる……と感じさせる一言でした。
第1話を展開で魅せる時代は終わるのかもしれない
私は以前なろう式追放モノテンプレートをご紹介しました。
また、小説家になろうで流行しているジャンル分析調査シリーズを書いたこともありました。
これらは「現在流行っている作品を把握して、テンプレートを理解し、それに沿って書いていくことで人気を獲得できる」という発想でご紹介しています。
ですが私が鬼滅の刃を読んで感じたのは、お話自体はテンプレートに沿っていても(鬼滅の刃も、お話自体はシンプルで、家族を殺されて鬼に復習する復讐劇です)、人気を獲得できるかどうかは台詞の力を始めとする各作家の才能に委ねられているということです。
Web小説が興隆し、ランキングなどから読者の趣向にそった作品が書かれるようになり、人気を獲得しています。いまはまだ人気小説に対し、「あの作品は人気小説のパクリだ、テンプレート通りだ」と批判する人もいます。
ですが、じきに、小説を書くためのノウハウが整備され(このサイトもその力添えになることを目指しています)、テンプレートで戦うのが当たり前の世界になってきたら、テンプレート通りに作業をすれば人気が獲得できる時代が終わります。その先には、台詞の力といった作家自身の創造力が必要となる時代が来るのだろうと感じます。
本当にクリエイティブを追求してきた小説家のみなさんには良い時代となるかもしれませんね。
展開に加えて台詞の力なども磨かなければ厳しい時代がくるとすれば、台詞の力を磨いていかねばなりません。ここからがいよいよ本題、なぜこの台詞は心に残るのか?を追求します。
台詞づくりのポイント〜なぜこの台詞は心に残るのか〜
台詞の力を身につけるため、「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」を分析していきます。
私がこの台詞を読んで感じた台詞づくりのポイントは以下3点です。
※ここからは、伝えたいことを明確にしたあとの、表現の部分に特化して書きます。「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」は、いってみれば「自分の生死を他人に委ねるな」ということです。まずは伝えたいことを平坦な言葉で書き出して、それを登場人物の台詞へ落とし込んでいく、二段階の作業が必要と考えると良いですね。
①文語表現を台詞に組み込む。
これは生殺与奪という単語に対してです。まず口語では利用しない言葉だなと感じ、新鮮味がありました。四文字熟語として紹介しているサイトもあるので、四文字熟語なのかもしれません。言われてみれば四文字熟語は口語としては使わない気がします。四文字熟語を多く知ることで、良い台詞を作り出せる可能性が高まるように思います。
②漢字一文字の持つ意味を深く知り、単語でつかうのか単体でつかうのかを選ぶ。
権利ではなく権と表現した点に大してです。権利ではなく権だけでも「《名・造》他人を支配することのできる力。他に対して自己を主張する資格。ちから。いきおい。」という意味があります。
私たちも普段使っている単語を分解して、漢字単体で使えないかを考えることで、良い台詞を作り出せる可能性が高まるように思います。
③単語、助詞、単語の文字数に注目し、リズムを考える
発音時の文字数ですので、小さい「つ」や伸ばし棒は1文字と数え、それ以外の小文字は0文字と数えています。
→例えば、奇数文字「の」偶数文字は鉄板かもしれない
せいさつよだつ(7文字)「の」けん(2文字)
ほくと(3文字)「の」けん(2文字)
ほんのうじ(5文字)「の」へん(2文字)
さいご(3文字)「の」せいせん(4文字)
ごとうぶん(5文字)「の」はなよめ(4文字)
ぬらりひょん(5文字)「の」まご(2文字)
→偶数文字「の」奇数文字も鉄板かもしれない
しんげき(4文字)「の」きょじん(3文字)
はな(2文字)「の」けいじ(3文字)
→助詞前後の単語の文字数をあわせるのも鉄板かもしれない
ふしちょう(4文字)「の」きしだん(4文字)
ちんもく(4文字)「の」かんたい(4文字)
とあるまじゅつ(6文字)「の」インデックス(6文字)
→7文字の単語はつい言いたくなるかもしれない
せいさつよだつ(7文字)「の」けん(2文字)
はがね(3文字)「の」れんきんじゅつし(7文字)
→3,5,7の魔力(助詞前後の単語の文字数を3,5,7のいずれかにする)
てにす(3文字)「の」おうじさま(5文字)
きめつ(3文字)「の」やいば(3文字)
→最後は「ん」か濁点で終わるといいかもしれない
例えば「生殺与奪の剣」と「生殺与奪の型」と「生殺与奪の槍」と「生殺与奪の樽」と「生殺与奪の家」と「生殺与奪の斧」でどれが言いやすいでしょうか(末尾の子音がそれぞれn,a,i,u,e,oです)。私は「生殺与奪の剣」のような気がします。最後が「ん」で終わることも、台詞のポイントのように感じます。
※最後が「ん」で終わっていると次の単語に繋げやすい。関西人の言葉が「ん」で終わるのは次々に話を繋げられるからだとか。
また、自分で口に出したとき、「ヒカルの碁」は言いやすいけれど「天気の子」はどうも言いにくい。最後を濁点にすることで言いやすくする効果があるかもしれません。
※「鬼滅のやいば」は言いやすい「鬼滅のやいは」だと言いにくい。
以上3点、「生殺与奪の権を他人に握らせるな!! 」を分析して台詞づくりのポイントを書きました。台詞の力を高める参考にしていただければ幸いです。
補足:前提条件として情報収集の心がけも必要
これは前提条件のようなものですが、幅広い情報を取り入れることも必要ですね。
例えば「生殺与奪の権を他人に握らせるな!!」であれば、生殺与奪の権利という言葉を知っているかどうか(Wikipediaで脚注を見るとアカデミック・ハラスメント関連の論文で使われている言葉に見えます)や、「生殺与奪の権を握る」という単語の使われている文章を読む機会があるかによって、台詞を思いつけるかどうか決まるかもしれません。
幅広く情報集を行って、気になった単語をメモしたり、記憶にとどめておく。これが良い台詞をつくり出す下地になります。
そういわれても興味のないジャンルの情報を集めるのは辛いという方もいらっしゃるでしょう。そういった人には、普段の仕事や勉強の中で、自分が専門としているジャンルにおいてカッコいいとされている台詞をメモしておくと良いですね。
私の出身学部である経済・経営学でも、かっこいい単語がたくさんあります。(神の見えざる手だったり、黄金律だったり、ビルトインスタビライザーだったり、テンションあがりますね)
ぜひ身近なところにあるカッコいい単語を見つけるよう心がけてみてくださいね。
以下に、情報収集に役立つコツを書いていますのでご参考まで。




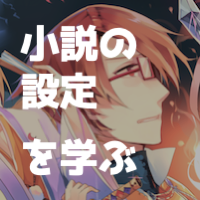






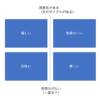

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません