日本の華族制度と西欧貴族制度の違い|公侯伯子男はどう訳された?
明治維新後、日本では華族制度が設けられ、西欧にならった貴族の爵位が導入されました。しかし、日本の華族制度とヨーロッパの伝統的な貴族制度には根本的な違いがあります。また、「公侯伯子男」という五つの爵位の名称は、西洋の称号を日本語に翻訳したものですが、その背景には中国古来の身分制度の影響がありました。本記事では、日本の華族制度と西欧貴族制度の違い、そして公侯伯子男という爵位が西洋の称号とどのように対応付けられたのかを解説します。
公侯伯子男は西欧の爵位をどう翻訳した?
明治政府が華族に授けた公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五等爵は、西ヨーロッパの貴族の称号を日本語に置き換えたものです。これらの漢字による爵位名は、もともと古代中国の身分制度(周代の諸侯の位階)に由来しています。明治11年(1878年)に明治政府の法制局が欧州貴族の称号を翻訳するにあたり、古来の「公・侯・伯・子・男」の五爵制を採用することを提案し、1884年の華族令で正式に五爵が定められました。その結果、Dukeに対して「公爵」、Marquisに対して「侯爵」、Count/Earlに対して「伯爵」、Viscountに対して「子爵」、Baronに対して「男爵」という訳語があてられました。このように「公侯伯子男」は欧米の貴族称号を置き換える訳語として誕生したのです。
ただし、一部には翻訳上の注意点もありました。例えば欧州の「Prince(プリンス)」という称号は本来君主の一族や小国家の君主を指しますが、日本語では「親王」など皇族に用いる語が別にあるため、華族の訳語には含めていません。また華族の最上位である「公爵」は英訳する際、しばしばPrinceと訳されました(実際、華族公爵の公式英訳はPrinceでした)。これは日本の「公」がヨーロッパの公爵(Duke)より広い概念(小国の君主=Princeにも相当)だったためですが、同じPrinceと訳される王族の称号と混同を生む原因にもなりました。このように、公侯伯子男は西欧の爵位と概ね対応しつつも、完全に一対一ではない部分もあったのです。
華族制度と西欧貴族制度の違い
制度の性格の違い: 西欧の伝統的な貴族制度は、中世の封建制に根ざしていました。貴族爵位は単なる名誉ではなく、本来は特定の領地を統治する権利(領主権)と結びついていたのです。例えば「伯爵」の称号はその伯爵領を治める領主であることを意味し、公爵や侯爵もそれぞれ公国・侯国の支配者としての権限を伴っていました。一方、日本の華族制度で与えられた爵位は家格を示す名誉称号の性格が強く、領地の支配権とは切り離されていました。華族公爵だからといって何か公国を治めるわけではなく、あくまで明治国家が旧大名・公家などを序列化して遇するための称号に過ぎなかったのです。
爵位の継承と複数称号: 西欧では一つの家が複数の爵位(称号)を持つことがしばしばあります。複数の領地を相続すれば、その分だけ公爵位や伯爵位など複数の称号を兼ねることになり、実際にヨーロッパの貴族社会では珍しくありませんでした。また、一家の家長が公爵位で、嫡男が従属する侯爵位を持つ(父の死後に公爵位を継ぐ)といった複数爵位の運用も一般的でした。しかし、日本の華族制度では一つの華族家が持つ爵位は原則一つのみで、複数の爵位を同時に保持することはありませんでした。華族の爵位はあくまで家単位の等級であり、欧州的な「○○公爵兼△△伯爵」といった概念は存在しなかったのです。
政治・社会的役割の違い: 西欧の貴族は歴史的に立法・行政・軍事において大きな権限や特権を持っていました(例:イギリスの貴族院、領主裁判権など)。日本の華族も明治憲法下で貴族院議員となる権利などは与えられましたが、その権限は限定的で、旧来の封建的特権は伴っていませんでした。華族制度は、むしろ国家に功績のあった者への栄典的な側面が強く、欧州のように各地を治める地方領主階級とは性質が異なります。第二次大戦後、華族制度は廃止されましたが、欧州でも貴族制度は時代とともに形骸化し、現在では多くが名誉称号として残るのみとなっています。
まとめ
以上、日本の華族制度と西欧の貴族制度の違い、および公侯伯子男という爵位名称の訳出について解説しました。簡潔に言えば、西欧の貴族爵位は中世の封建領主の名残として成立し、日本の華族爵位は近代の名誉称号として制定されたという違いがあります。そのため、爵位に伴う領地支配や制度運用に差異が生じました。また、公侯伯子男という名称は西洋の称号を翻訳する際に中国由来の用語をあてたもので、明治期に伝統と近代化を折衷する形で生まれたものです。
華族制度は消滅しましたが、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」という五爵の枠組みは、今なお歴史用語やフィクションの中で生き続けています。西欧と日本の貴族制度の違いを理解することで、それぞれの社会や文化の特色について一層深い洞察が得られそうですね。


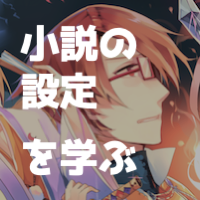








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません